近藤誠さんについては複雑な思いがあります。私は20年前の近藤ブームも体験しています。その時は患者家族として本を手に取りました。そしてそのことがきっかけで、医療者にお任せが当たり前の医療の在り方に、初めて疑問を抱くようになります。当時の著書には、今出ている本には感じられない、「患者への思い」があったと私は思っています。そんな当時のことを回想して書いています。
「患者に新たな選択肢」(2015年6月号掲載)
今、近藤誠さんの本がベストセラーになっています。『医者に殺されない47の心得』など多数の著書で、「がんは放置すべし」「抗がん剤は効かない」などと主張しています。
近藤さんの本が初めて話題になったのは、1996年『患者よ、がんと闘うな』が出版された頃でした。この時期、母が希少がんと呼ばれる、患者数の少ないがんに侵されていることが判明し、私もすがるように何冊か読みました。
じっくり読む余裕はなく拾い読みでしたが、この本からは、医療は医療者にお任せではなく、たとえがんでも、患者は情報を集めて治療について自らも考えなくてはいけない、ということを学びました。
とはいえ母の場合、珍しいがんだったため関連書籍も見つからず、ネットも発達していなかった当時は、必要な情報を得ることが困難でした。ましてや進んだ状態で見つかり、考える時間もなかったので、せいぜい知り合いの医師に、手術をすべきかどうかを相談することくらいしかできませんでした。
手術前には主治医の勧めで、当時とても珍しかった、がんを早期発見できるという触れ込みのPET検査まで受けに行き、一応転移がないことも確かめて手術に臨みました。にもかかわらず母は術後2か月ほどで亡くなってしまいます。広範囲に臓器を切除したあとは多くの管につながれ、退院できないまま病院で最期を迎えたのです。
その後長らく、本当にこの治療でよかったのか、自問自答が続きました。こういう提案ができたのでは、こんな疑問もぶつけられた、などと何度も考えてしまうのです。
昨年自分ががん患者になって、『患者よ、がんと闘うな』や『がん専門医よ、真実を語れ』を改めてじっくり読んでみました。20年も前にこれだけのことを書かれたことに驚きます。特に専門である乳がんに関する部分は、本で予測されていたことが今現実になっていたりもします。
当時の著書では、「現在転移がない早期がんを放置したときに、将来絶対転移しないわけではないので、その可能性を重視すれば早期がんを治療することはやむをえない」や、「がんもどき理論はあくまでも仮説だ」とも書かれていて、きちんと読むと、内容はタイトルほどセンセーショナルではありません。
また「かりに手術を受けても大手術による合併症や後遺症で苦しむことがないように」という考えも、私には共感できる部分でした。母のように大量の臓器を取る治療に何のメリットも感じられなかったからです。
近藤さんの出版による情報公開は、乳がんの温存療法の普及にもつながり、予後や治療後の人生をも考えた提案は、患者に新たな選択肢を作ったと言えます。医療の第一線にいながら、干されることも覚悟の上で、それまでの医療の在り方に疑問を呈したのは意義深いことでした。
一方昨今出されている本はというと、今の医療との対決色がより鮮明になって、論調は同じながらも、どこか患者に持論を押し付けているだけのような印象を抱きます。続きは次回に。

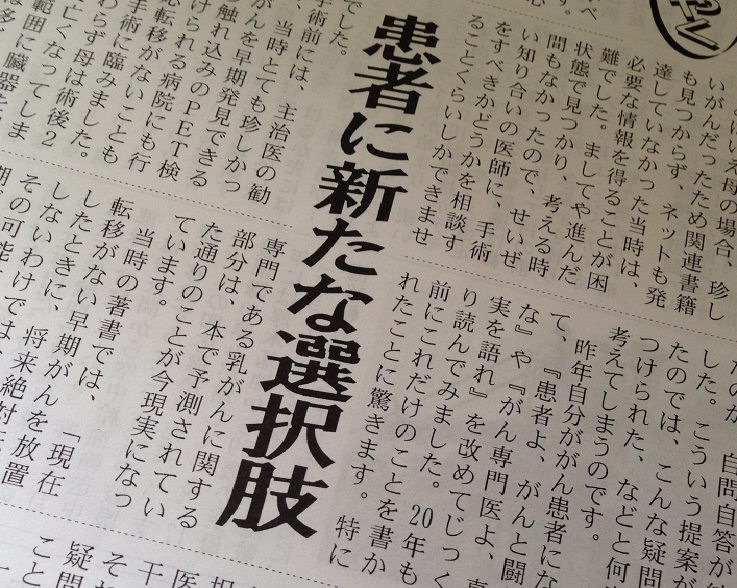
コメント
コメントはありません。